○公文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年6月30日
訓令第1号
(実施範囲)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 削除
(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(3) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの
(4) 表彰文、儀式文その他町長が縦書きを必要と認めたもの
(実施の時期)
第2条 公文書の左横書は、昭和35年7月1日から実施する。
(実施の要領)
第3条 公文書の左横書き実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和40年訓令第5号)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年訓令第7号)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
参考
左横書き公文書の書き方
1 公文書の書き方
左横書きにおける公文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。
(1) ふりがなの付け方
漢字のふりがなを付ける場合は、その字の上に付ける。
(2) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは中央に書く。
(3) 数字の書き方
ア 数字は、次に掲げるような場合を除いて、アラビヤ数字を用いる。
国有名詞 (例)四国 九州 二重橋
概数を示す語 (例)三・四日 四・五人 数十日
数量的な感じのうすい語 (例)一般 一部分 四分五裂
単位として用いる語 (例)220万 7,200億
慣用的な語 (例)一休み 三間続き 三月(みつきと読む場合)
イ 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、電話番号など特別なものは区切りをつけない。
ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
よい | わるい | ||
小数 | 0.123 | 0,123 | |
分数 |
| 2分の1 |
|
帯分数 |
|
| |
エ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
日付 | 時刻 | 時間 | |
普通の場合 | 平成5年1月5日 | 10時35分 | 10時間35分 |
省略する場合 | 平成5.1.5 |
(4) くぎり符号の用い方
ア 句読点は、「。」及び「、」を用いる。
イ 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合、見出し記号に付ける場合及び省略符号にする場合に用いる。
(例) 1,234.00円 0.12 平.5.1.1 N.H.K
ウ 「・」(なかてん)は、事物の名称を列挙するとき、又は外来語の区切りに用いる。
(例) 熊本市・飽託郡・上益城郡では
サウジ・アラビヤ
エ 「~」(なみがた)は、「……から……まで」を示す場合に用いる。
(例) 第1号~第9号 東京~大阪
オ 「―」(ダッシュ)は、語句の説明やいいかえなどに用い、丁目・番地を省略して書く場合に用いる。
(例) 信号灯 赤―止れ 青―進め 霞ケ関2―1(霞ケ関2丁目1番地)
カ 「「」」(かぎ)、「()」(かっこ)などは、縦書きの場合と同様である。
(5) くりかえし符号
「々」(漢字のくりかえし符号)だけを用い、かなのくりかえし符号(「ヽ」、「 」)は、使用しない。
」)は、使用しない。
(6) 見出し符号の用い方
項目を細別するときは、次の例による。
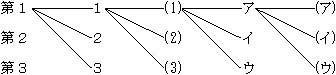
見出(符号は句読点「、」を打たず1字分空白として次の字を書き出す。
2 公文書の書式
公文例規程(昭和40年訓令第2号)の定めるところによる。
参考としておもなものの書式を掲げると次のとおりである。
(達の書式)
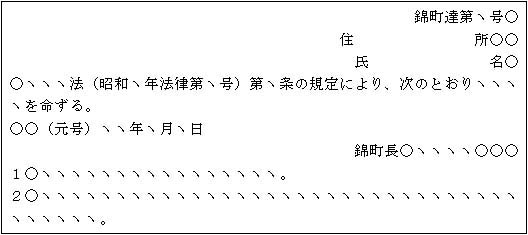
(指令の書式)
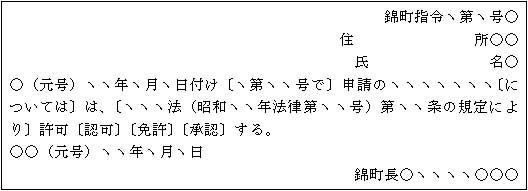
(往復文の書式)
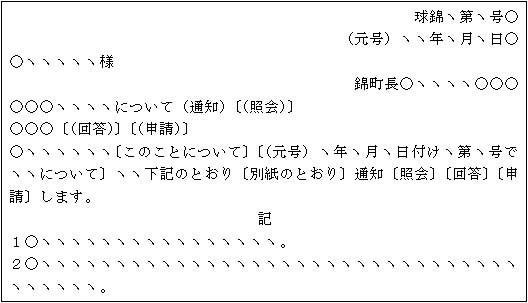
左横書きの実施に伴う文書のとじ方
文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。
1 縦書きの文書のみをとじるときは右とじとする。
2 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。
3 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
4 B5判用紙を横長に、B4判用紙を縦長に用いた場合は、上とじとしてもよい。



